今回はいよいよ、いよいよ塗装。
飛行機模型において塗装はクライマックス中のクライマックスだ。これまでの製作段階では痛む腰を気遣って一日一時間ほどで作業を終えていたのだが、今回ばかりはそうもいかない。休日の朝にスタートだ。入念に腰痛体操をして、医者からもらった久光製薬のモーラステープを体中に貼りまくって万全の体制で臨む。無制限一本勝負、長丁場の死闘となるのは覚悟の上だ。
なので下準備としてカウリングと白帯、白十字、下面色は事前に塗っておく。いわゆる仕込みである。まるで「世界の料理ショー」のグラハム・カー並みの段取りのよさではないか。おいスティーブきのう塗っといたカウリングどこやった?まさか食べちまったんじゃないだろうな?
カウリングのイエローの色調は明るめで派手さを抑える、のは前回の計画通り。軽くサラっと言ってみたが、いつもうまくいかず苦心している。胴体帯や味方識別色といった補助的なカラーはついつい面倒がって瓶ストレートで塗ってオモチャ臭くしてしまう。
それが嫌なものでウォッシングなどで彩度を下げるのだが、もろともに明度まで落ちてしまってなんだか汚らしい作品になりはてるのが自分の通例だ。そこらへんの色彩計画にも気を遣って、最初からきちんと色を作っておこう、というわけだ。


黄橙色とキアライエローの中間くらい、といっても両者を単に混ぜるのではなく、キアライエローに少量の「色の源」マゼンタ、微量のシアン、白などを使って彩度を殺しつつ黄橙色にじり寄せていく。絵皿で予行演習しているのはいきなり瓶で作るといつの間にか量が増えて大量の失敗塗料が出来上がって処理に困ったちゃん、という苦い経験が多々あるからだ。予行演習での調合は感覚で再現する。
次に胴体の白帯と尾翼の白十字(白十字はデカールは使わず手書きし、紋章部分だけ切り抜いて貼る予定)これも純白ではなくデカールの国籍マークに合わせて調色する。こちらがそのデカールの状態。それではサンボルさん、どうぞ。
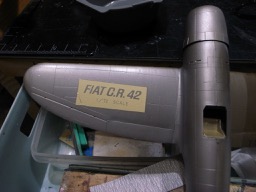
「何べんも出すなや恥ずかしいやんけ」
黄ばんだ白というよりもはや薄汚れたベージュとなっている。オカンのババシャツかい!さすがにそこまでの色にするのも気が引けるから、全体として違和感がない程度の色調に近づけるにとどめておく。胴体帯は国籍マークと隣同士に並ぶ訳ではないのだ。
そう、イタリア機には胴体に国籍マークがない。今更ながらその事に気づいたが、味方から誤射されたりしなかったのだろうか?...誤射されるほど沢山の味方機はいなかったか、そうかそうかそらよかった。
白にいきなり茶色を混ぜると古本屋の岩波文庫「ブッテンブロオグ家の人々」の中表紙みたいにエラくひなびた色になってしまう。前述のクレオス「色の源」イエロー、マゼンタを加えていって様子を見る。なんだか溶けたハーゲンダッツっぽくなった。うまそうだからって飲むんじゃないよスティーブ。

そこでごく微量のシアンとイエローを垂らして引き締めた、のが上の画像。甘ったるいクリーム色からわずかに緑味を感じる上品な象牙色となってニンマリ。これは以前タイタニック号を作った時に覚えたレシピ。

自分としては黄色がちょいと派手めに感じるがここは我慢我慢。カウリングの無塗装銀の部分は太すぎてピカチュウが結婚指輪を二本はめたみたいになった。ここだけ後でスミ入れ等で落ち着かせよう。
白部分を吹き付けマスキングしたら下面色のブルーグレーを吹く。うっかり上翼と支柱を忘れるところだった。何の為に半泣きになりながら支柱を削ったのかわからんがな。
、、、と、ここまでが前日までの下ごしらえとなる。
一晩冷蔵庫に入れた、じゃなくて乾燥させたファルコの下面をマスキング。イタリア機は翼の下面にも上面色が少し回り込んでいる。何故かはわからない。何故かはわからないが洒落ては見える。下から見上げた場合の被視認性は確実にあがるから英軍の高射砲兵には喜ばれたろう。。。胴体の境目は最近流行のMrペタリ、ではなくブルータップを使う。コクピットには某百均製のパチモンを使ったがちょっとネチャネチャして心配だった。
さて準備が万端整ってまな板の上に乗ったファルコに上面ベース色の自作イエローオーカーをプシシシと吹き付ける。

南米に生息する齧歯類みたいになったファルコ。

iPadの画面で色調見比べても意味ないような。。。
何となく黄色っぽい気もするが、まあこんなものだろう。
そして次は迷彩塗装だ。。。